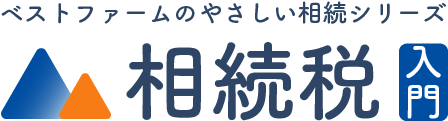暦年贈与は、贈与における年間110万円の非課税枠を活用した生前対策のひとつです。暦年贈与をうまく利用することで、相続税の負担を軽減し、計画的な資産移転を行うことが可能です。しかしながら、2024年から施行された法改正により、暦年贈与は使い方がやや難しくなり、活用の難易度は高くなったように思います。本記事では、暦年贈与の基本や非課税枠の活用法、贈与税の計算方法、そして相続時精算課税制度との違いについて詳しく解説します。また、注意点や併用可能な非課税制度についても説明します。
暦年贈与の基本
暦年贈与の定義
暦年贈与は「暦年課税制度」の特徴を活かして行う生前対策です。暦年課税制度とは贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計に対して課税されます。 暦年課税制度には、贈与を受ける人ひとり当たり年間110万円の控除額が認められており、贈与額が110万円以下であれば贈与税を申告する必要はありません。110万円の基礎控除額を超えた分に対しては、贈与額に応じて課税される仕組みです。暦年贈与はこの年110万円の基礎控除額を使って少しづつ財産移転を行う生前対策です。中長期的に毎年110万円以下の贈与を繰り返し行い、贈与税をかけずに子世代に財産を移転させていくことが暦年贈与の目的になります。
暦年贈与での基礎控除額110万円の考え方
大前提として、贈与税は財産をもらった人(受贈者)が納付するものです。よって、基礎控除額110万円は受贈者が税金なしで贈与を受けていい上限額と考えます。例を挙げます。同じ年に父親が80万円、母親が50万円を子に贈与した場合、子は合計して130万円の贈与を受けたことになりますので、「110万円の基礎控除額を超えた」と考えます。つまり、一人からの贈与が110万円以内に収まっていたとしても、複数人から贈与を受けて110万円を超えてしまえば、贈与税がかかります。
暦年贈与で基礎控除額110万円を超えた贈与をした場合
基礎控除額を超えた場合、その超過分に対して贈与税が課税されます。累進課税により、贈与額が多いほど高い税率が適用されます。例えば、贈与額が150万円の場合、基礎控除額を超えた40万円(150万円 – 110万円)が課税対象となります。贈与税の納付額はこの超過金額が上がるほど税率が高くなり、納付額が大きくなる仕組みです。
贈与税の計算方法
先ほど述べたように、贈与税は年110万円を超過した部分に対して課税されます。計算式で表すと下記のようになります。
前述した通り、計算式の「贈与税率-控除額」の部分は一律でなく、110万円を超えた金額分に応じて税率が階段式に設定されています。この贈与税率の設定は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の関係性によって、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分けられます。下表のとおり、一般贈与財産と特例贈与財産の対象とそれぞれの贈与税の速算表を記載します。特例贈与財産の方が一般贈与財産より税率が低くなっています。
一般贈与財産の税率(一般税率)と特例贈与財産の税率(特例税率)
| 関係性 | 例 | 税率 |
| ・直系尊属(※)以外からの贈与・直系尊属(※)から 未成年者への贈与 | ・夫婦間で贈与する場合・兄弟間での贈与する場合・父母から未成年の子へ贈与する場合・祖父母から未成年の孫へ贈与する場合 | 一般贈与財産 |
| ・直系尊属から成年者への贈与(※2) | ・父母から18歳以上の子へ贈与する場合・祖父母から18歳以上の孫へ贈与する場合 | 特例贈与財産 |
※ 父母・祖父母など自分より前の世代
※2 贈与される年の1/1に受贈者が18歳以上であること
一般贈与財産の贈与税の速算表(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ─ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例贈与財産の贈与税の速算表(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ─ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
暦年贈与の手順
暦年贈与の手順をこちらで解説します。
1. 事前合意する
贈与の内容を贈与者と受贈者で合意します。
2. 贈与契約書を作成する
贈与契約書は、贈与の事実を明確に記録し、後々のトラブルを防ぐために重要です。作成する際には以下の項目を記載します。
贈与者と受贈者の情報:名前、住所
贈与の内容:贈与する財産の詳細(例:現金、土地、株式)
日付:贈与契約書を作成した日付と具体的な贈与実施の日付
贈与の方法:振込先など
3. 署名・押印する
贈与者と受贈者の双方が署名・押印を行います。
4. 保管する
作成した贈与契約書を贈与者と受贈者がそれぞれ保管し、必要に応じて提示できるようにします(つまり二通作成する必要があります)。受贈者が未成年の場合は、親権者の住所、氏名を記入の上、署名・捺印します。
5. 財産を実際に渡す
贈与契約書に記載した内容通りに財産を渡します。財産の受け渡しは現金で行わないようにしましょう。贈与の客観的な痕跡が残らないためです。
6. 110万円を超える場合は贈与税申告
1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた贈与額の合計が、年間110万円を超えたら贈与税申告を行いましょう。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に申告します。
暦年贈与の注意点とポイント
暦年贈与の注意点1:定期贈与
暦年贈与として、年110万円以下で贈与を行っていても、税務署から疑いを持たれ課税対象とされるケースがあります。それが、「定期贈与」です。定期贈与とは、あらかじめ贈与者と受贈者との間で、まとまった金額を一定期間に分割して受け渡すことが決められている贈与のことです。例えば、毎年100万円ずつ10年間に渡って1,000万円贈与を受けることを約束した贈与契約書を作成した場合、1,000万円分の権利を贈与されたとみなされ、贈与税の対象として扱われます。そのため、暦年贈与では毎年その年の分の贈与に関する贈与契約書を作成する必要があります。毎年贈与契約書を作成しなければならないなんて、とても面倒ですね。しかし、これをきちんとやっておかないと、税務署に毎年の贈与を疑われた場合に、説明することができません。誤った贈与契約の内容とならないように、贈与契約書は適切に作成しましょう。
よく似た言葉「連年贈与」とは?
定期贈与に似た言葉で「連年贈与」というものがあります。どちらも毎年贈与をおこなう点では同じです。しかし、税務署側の視点で、たまたま毎年贈与を行っていただけと認められたら連年贈与として扱われ、あらかじめ約束した金額を分割して贈与しているとみなされたら定期贈与として扱われます。連年贈与ならセーフで、定期贈与ならアウトということです。
暦年贈与の注意点2:名義預金
定期贈与と同じく暦年贈与の失敗の原因となるのが、「名義預金」です。名義預金は、受贈者の名義で贈与者が預金を預けている状態のことです。よくあるのが、祖父母が孫のために孫名義の口座を勝手に作り、毎年100万円を貯金しているといったケースです。口座名義人である孫がその口座の存在を知らない場合、贈与とは認められず、110万円の基礎控除額も使えません。110万円の基礎控除額の利用には、贈与者・受贈者の間できちんと合意があったことを客観的に分かるようにしておかないといけません。受贈者側が口座の存在を知らなかったり、お金を事実上使えない状態であったりすると、名義預金とみなされる可能性はかなり高いです。口座の名義が孫や子になっているだけでは、暦年贈与にならないので注意しましょう。
暦年贈与の注意点3:「年110万円」の控除は受贈者一人の上限額
繰り返しになりますが、年110万円の控除は受贈者一人の控除の上限です。一人の受贈者が複数人から贈与を受けた場合、贈与者一人あたりの金額が110万円以下でも、受け取った金額の合計が110万円を超えていれば、贈与税が課税されます(後述しますが、異なる受贈者からの贈与で、相続時精算課税制度を利用している場合を除く)。
暦年贈与を成立させるためのポイント
上記を踏まえて、暦年贈与を成立させるポイントを以下にまとめます。
①贈与契約書を毎年作成する
②「毎年100万円ずつ10年間に渡って1,000万円贈与」といった複数年の贈与契約をしない
③預金の運用は預金の名義人(受贈者)が行う
④複数の人から贈与を受ける場合は合計110万円を超えた分から贈与税が発生することを忘れない
相続時精算課税制度との違い
贈与において、暦年贈与と双璧を成す制度が「相続時精算課税制度」です。あわせて概要を抑えておきましょう。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、暦年課税制度と同じく贈与時の課税方法です。60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与する場合に選択できます。この条件に当てはまる贈与を行う際には、相続時精算課税制度か暦年課税制度のどちらを選ぶのか検討しなければなりません。なぜならば、相続時精算課税制度の利用を開始すると、その受贈者と贈与者の間での贈与については暦年贈与に戻すことができないからです。
相続時精算課税制度と暦年贈与との違い
対象者の違い
暦年贈与は受贈者・贈与者が誰であっても利用できるのに対し、相続時精算課税制度は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限定されています。
控除額の違い
相続時精算課税制度には2つの控除があります。ひとつ目は、2,500万円の特別控除枠です。相続時精算課税制度を選択すると累計2,500万円まで贈与税なしで贈与することができます。ただし、贈与した人が亡くなったら、贈与された2,500万円分の財産は相続財産として扱われ相続税として課税されます。
ふたつ目は、暦年贈与と同じく年110万円の基礎控除額です。控除額は同じですが、内容は異なっており、暦年贈与の年間110万円の基礎控除額は、贈与者が亡くなる前、一定の期間内(3~7年以内)贈与は生前贈与加算され、相続財産として扱われるのに対し、相続時精算課税制度での贈与は一切加算されません。つまり、相続時精算課税制度における年110万円は、無税での贈与が約束されている控除額なのです。
110万円を超過した分に対する税率の違い
暦年贈与は110万円の非課税枠を超えた場合の税率は、前述した通り贈与額により10%~55%であるのに対し、相続時精算課税制度では累計2,500万円までの贈与には贈与税は課税されず、2,500万円を超えた部分に対して一律20%です。
相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け
上記の違いを見ると相続時精算課税制度の方が使い勝手が良さそうに見えますが、暦年贈与も使い所があります。次のようなケースでは特に暦年贈与による節税が有効と考えられます。
孫への贈与
先ほど、「暦年贈与の年間110万円の基礎控除額は、贈与者が亡くなる前、一定の期間内(3~7年以内)の贈与は生前贈与加算され、相続財産として扱われる」と説明しました。この生前贈与加算の対象となるのは、贈与者が死亡した際に財産を相続・遺贈で取得する人だけです。つまり、一般的な相続の場合、子が相続するはずなので、孫への贈与分は生前贈与加算の対象外となります。ゆえに、相続人にならない孫への贈与は有効な節税手段となるのです。
父と母で相続時精算課税と暦年贈与を使い分ける
相続時精算課税制度では、贈与者・受贈者ごとに適用できます。例えば、父から息子には制度を適用し、母からは適用しないといったことができます。父からの贈与と母からの贈与に対して、いずれも相続時精算課税制度を選択すると基礎控除額は二人分で年合計110万円までになります。父からの贈与と母からの贈与が両方とも暦年課税制度であれば、非課税枠は二人分で年合計110万円までです。しかし、一方が相続時精算課税制度を選択し、もう一方が暦年課税制度のままの場合は、それぞれの基礎控除額110万円で年間の基礎控除額が220万円になります。これは課税制度ごとに基礎控除額が設定されているためです。
暦年贈与と併用可能な非課税または控除制度
要件を満たせば贈与税が非課税になる制度や特例が実はいろいろあります。下記に暦年贈与と併用可能な非課税制度や特例をまとめました。節税をお考えの方は、どのような制度で、その要件がどういったものか、なんとなくでも知っておくと、節税の幅が広がることでしょう。 いずれも適用にはもう少し複雑な要件や手続きがありますが、ここでは簡略化してお伝えします。
住宅取得等資金
父母や祖父母など(直系尊属)からの贈与を、自分の居住用の住宅家屋の新築、購入、または増改築などの費用にする場合は、最大で1,000万円までの贈与は非課税になり、暦年贈与または相続時精算課税制度と併用できます。
住宅取得等資金の非課税を適用した部分は、生前贈与加算されません。
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
20年以上婚姻期間が続いている夫婦の間で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合、贈与税の課税価格から2,000万円まで控除(配偶者控除)することができ、暦年贈与と併用できます。こちらの控除を適用した部分は、生前贈与加算されません。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与の非課税も暦年贈与または相続時資産課税制度と併用可能です。教育資金の一括贈与の非課税は、親や祖父母(直系尊属)から子や孫へ教育資金として最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。子または孫は30歳未満で所得が1,000万円以下でなければいけません。贈与者(親や祖父母)は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、受贈者(子や孫)は教育資金の請求書などを金融機関に提出することで、贈与税非課税でお金を使うことができます。受贈者が30歳になると、金融機関との契約は終了し、口座に残っていたお金は自動的に贈与税の対象となります。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税とは、直系尊属(親や祖父母)から子や孫へ(18歳以上50歳未満)将来結婚や子育てに使うお金として最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。教育資金の一括贈与の非課税と同じく、暦年贈与または相続時資産課税制度と併用が可能です。また、同じように贈与者は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子や孫は結婚や子育てにお金を使ったことを証明する領収書等を提出します。契約が終了した後も口座に残ったお金には、贈与税が課される点も同じです。
まとめ
暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除額を活用して資産を計画的に移転することで、相続税の負担を軽減する方法として使われてきました。しかしながら、現在、贈与と相続を一体に課税する「一体課税」の方向に税制は動いてきており、2024年に生前贈与加算の期間が3年から7年に段階的に延長されることになりました。。その結果、暦年贈与の使いどころが難しくなってきているのが実情です。ただ、現時点ではまったく使えなくなったわけではありませんので、専門家と相談しながら適切な対策をすることをお勧めします。税制は毎年少しずつ変わるので、最新情報を知っている税理士などを気軽に頼ってみましょう。